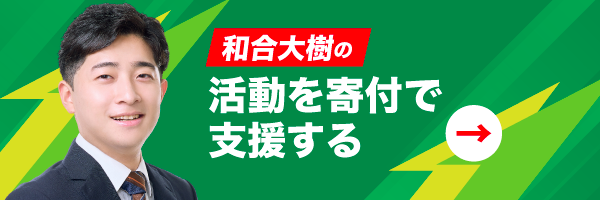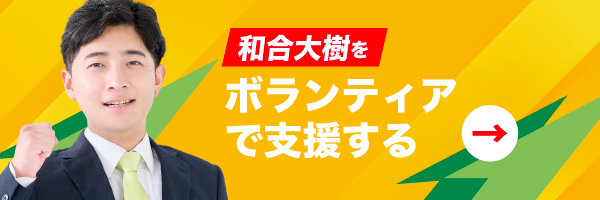出産は、人生の中でもっとも大きな転機のひとつです。喜びの一方で、身体の変化や孤独、不安と向き合う時間でもあります。僕自身、父親として出産や育児の現場に立ち会い、その支えの必要性を強く感じました。
仕事の責任、家事や育児の時間、経済的な不安が重なり、余裕をなくしてしまう瞬間も夫婦で多々あります。
そのとき感じたのは「家庭の努力だけでは子育てを支えきれない」という現実です。自分自身が支援を受ける立場でもあるからこそ、同じように悩む家庭が孤立しない仕組みが必要だと痛感しました。
出産後の母子を支える体制
川崎市では、初めての育児で退院後に不安を感じる方や、授乳がうまくいかない方、赤ちゃんのお世話や生活リズムに悩む方、出産や育児の疲れから体調がすぐれない方などを対象に、助産師や保健師によるサポートを受けられる支援体制が整備されています。
出産後の母子を支える取り組みは着実に進んでいますが、その支援をさらに拡充し、より多くの家庭に届く仕組みを根付かせていくことが課題です。
利用方法や費用の負担、予約のしやすさなど、実際に支援を必要とする家庭がスムーズに利用できるよう、現場に即した制度運用とサポートの強化が求められています。
また、出産後の母親の約10〜15%が「産後うつ」を経験するといわれ、心身の不調を早期に支えられる体制づくりも重要です。こうした中で、母子の心身の健康を守る体制をさらに強化し、誰もが安心して頼れるまちをつくることが必要です。
現場から届く市民の声
- 誰でもいいから、悩みや不安を聞いてほしかった
- 支援施設やイベントに行くのに一人で行くのにハードルを感じた
- 制度の存在をもっと早く知っていれば、あのとき無理をしなかったと思う
地域周りや、子育て支援活動をしている中、その活動で出会った方からさまざまな声を聞きます。
出産や育児の中で感じる不安や孤独は、誰にでも起こりうることです。それでも、誰かに話を聞いてもらえるだけで、心が少し軽くなる。そんな頼れる場が身近にあることが、どれほどの支えになるかを、僕は地域の現場で何度も見てきました。
切れ目のない支援の拡充
妊娠期から産後までを支える体制は、まだ十分に整っているとは言えません。私、和合大樹は、産前産後ケアの支援をさらに拡充し、母子の心身の健康を守る体制を強化します。
妊娠期から産後まで切れ目のない支援を整え、支援が必要なすべての家庭に、確実に届く仕組みをつくります。
「子育てを家庭の努力に任せる社会」では未来が続きません。「子どもを育てることは、誰かに頼ってもいい」そんな社会の空気を、川崎から広げていきます。